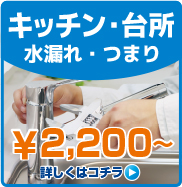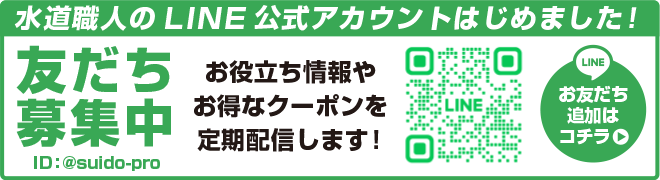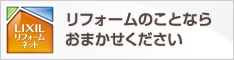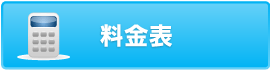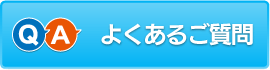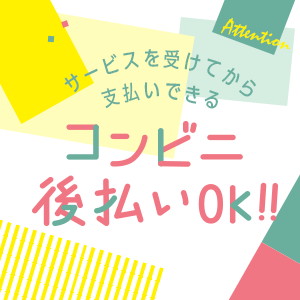水のコラム
トイレが水浸しになる原因とは? 自力で直せるケースや予防策もあわせてご紹介

普段使用しているトイレが突然水浸しになって困った経験はないでしょうか。
水浸しのトイレを掃除するのも大変な労力なうえ、雑菌やカビなどが繁殖しやすいため衛生的にも良いとは言い難いものです。
今回はトイレが水浸しになる原因と予防策についてご紹介します。
自分で直せるケースと業者に依頼したほうが良いケースもあわせて解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。
トイレが水浸しになる原因

まずは、トイレが水浸しになってしまう原因についてご紹介します。
トイレの設備から水漏れしている
トイレが水浸しになってしまう多くの原因は、トイレの設備に何らかの不具合や劣化が生じてしまったためです。
水が漏れている箇所によって、トイレのどの部品が悪くなっているのかを判断することができ、スムーズに修理などを行うことができるでしょう。
トイレタンク
タンクから水がポタポタと漏れている場合、タンク自体にひびや傷ができている可能性と内部の部品が劣化している可能性が考えられます。
タンクは陶器で作られることが多く、高い耐久性を誇りますが、地震や経年劣化によってダメージが入っていった結果、亀裂が入って水が染み出してしまうのです。
内部部品の不具合としては、ゴムフロートに汚れが付着していたり、ボールタップが劣化して欠けてしまったりすることがあります。
どちらもタンク内に溜める水の調整や制御を行うためのものです。
この他にも、防露材の膨張やパッキンの劣化などさまざまな部品の不具合も、タンクの水漏れ原因となる可能性があります。
便器
タンクと同じく陶器製となっていることが多い便器ですが、日常的な小さな衝撃や地震などのダメージが溜まることでひびが入ってしまうことがあります。
またトイレ掃除の際に熱湯をかけている場合も注意が必要です。
トイレは陶器製のポットなどと同じ材質でできていますが、形状が複雑で陶器の断面が厚い部分と薄い部分が交差しています。
そのため、熱いお湯に強いというわけではないのです。
茶渋などを取る感覚で熱湯をかけて掃除をすると、極端な温度差で便器の劣化を早めてしまいかねません。
ウォシュレット
ウォシュレットから水が滴っている場合は、給水部分のノズルやパイプなどの劣化が原因となっている可能性があります。
ただウォシュレットは、電気系統の部品も併せ持つ大変複雑な構造です。
水が少量だけであったりウォシュレットを使用した時にだけ水が出たりする場合は、ウォシュレットのどの部品に異常が出ているかを特定することが難しいでしょう。
止水栓・給水栓・洗浄管
トイレの水を調整する止水栓をはじめとしたタンクや便器と繋がる周囲の配管に不具合が起きている可能性があります。
接続部分のパッキンなどが年月と共に擦れてしまい、役割を十分に果たせなくなっていることが主な原因です。
パッキンの寿命はおよそ10年程度とされていますが、使用頻度に関わらずある程度の時期に交換する必要があります。
また、少しずつ日々の小さな衝撃によって配管の接続部分のナットやネジが緩んでいたり、地震などの衝撃を受けて配管に亀裂などが入っていたりすることもあります。
掃除などを行う際に定期的に締め直したり、配管に問題がないかを業者に点検したりしてもらうことが大切です。
水漏れ以外でトイレが水浸しになる原因
トイレが水浸しになるのは、必ずしも水漏れのみが原因とは限りません。
水漏れ以外にも、以下のことが原因で水浸しになることがあります。
- ●湿気による結露
- ●尿が漏れている
- ●逆流している
湿気による結露
梅雨や冬の暖房器具による温度差で湿気が生じたことによる結露が原因で、床に水が広がっていることもあります。
タンクには防露材が備わっていることが大半ですが、タンクだけでなくトイレ全体が濡れている場合は家の間取りや地域の環境によるところが大きく影響しています。
放置しているとカビなどの温床になることもあるため、こまめに掃除するようにしましょう。
尿が漏れている
トイレの床などが一部水浸しになっている場合は、尿が便器から漏れていることが原因かもしれません。
用を足す際に浅く腰掛けていたり、便器に入ったひびなどから染み出したりすることで、一部に水たまりを作ってしまうことがあります。
尿かどうかは床にできた水たまりの色や臭いで判断することができるため、便器などに亀裂などがないかなどを確認しましょう。
逆流している
排水管や排水桝にトイレットペーパーなどの異物や長い期間の汚れが付着することでつまりを起こし、逆流してしまっていることがあります。
逆流の場合は汚水が溢れてきているため、速やかに対処する必要があります。
また近年の大雨などによる災害によって、下水の処理能力が追いつかずにトイレへ下水が逆流してしまうこともあるため、逆流が予想されるほどの災害時には、床にシートを敷いておいたり水のうを準備しておいたり、事前に対処しておくのがおすすめです。
水浸しの原因を突き止める
トイレが水浸しになっている原因によって、対処の方法が変わってきます。
しかし、床下や壁の中にある配管の異常によって水浸しになっている場合、素人が原因を特定することは困難です。
どこから水が漏れているかわからないという場合は、速やかに専門の業者へ連絡して修理を行いましょう。
トイレの水浸しは自分で直せるのか

最近では多くの修理に関する情報がネットなどで手に入るため、業者を呼ばなくても自分で修理したいと思われる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、トイレ修理は自力で直しても問題ないケースと業者に依頼する必要があるケースを判別しなければいけません。
せっかく修理をしてもまた水が漏れてきてしまったり、さらに悪化して費用が高額になってしまったりすることもあります。
自力で修理できるケースは
DIYにさほど慣れていなくても自力で修理することが可能なケースは以下のとおりです。
- ●パッキンの交換
- ●ナットやネジなどを締める
- ●温水便座の交換
パッキンの交換
パッキンは寿命が10年程度といわれています。
ただし、多くのパッキンは材質がゴムで作られているため、劣化すると繊維などがボロボロと欠けてきます。
掃除などを行った際、周囲にゴムのカスや黒い汚れが出てくる場合は、年数が経っていなくとも交換するのがおすすめです。
パッキンの交換は自分で交換することも可能なため、ホームセンターやネット通販でパッキンを購入することもできます。
しかし、パッキンにはさまざまな種類があるため、事前に交換するサイズや形状を確認しておきましょう。
ナットやネジなどを締める
止水栓や給水栓など配管の接続部分は、年月と共に細かい衝撃が重なることでだんだんと緩んでいきます。
接続部分から水が垂れているという場合は、六角レンチなどの工具でナットやネジを締め直しましょう。
また便器やタンクといった陶器製のものと配管を繋ぐナットを締める際は、強く締めすぎてしまうと逆に周囲が欠けて破損してしまうことがあります。
水が漏れ出さない程度の適度な締め直しを行うように、十分注意して作業するようにしてください。
温水便座の交換
ウォシュレットなどの温水便座は複雑な構造となっていますが、ノズルやフィルターといった部品は簡単に交換することができます。
どこまで自力で対処できるかはメーカーによって異なるため、説明書などをよく読んで作業を行いましょう。
電気系統に関する故障の場合は、メーカーが修理を断る可能性があるため、分解などは行わないようにしてください。
トイレタンクや配管などは業者に依頼する
タンクや配管自体に以上や破損が見られる場合、自力で修理を行うことはおすすめできません。
タンクは重量があるため、重いものを持ち上げたり下ろしたりする作業に不慣れな方では怪我や事故などを起こしてしまうかもしれません。
また床下や壁の中を多くの配管が通っているため、専門知識のない方が異常のある配管や問題のない配管を見分けることは困難です。
自分でできる範疇にないと判断した場合は、すぐに業者に依頼して修理してもらいましょう。
トイレを水浸しにしないための予防策は

トイレが水浸しになることを防ぐためには、どんな対策をすると良いのでしょうか。
トイレが水浸しになることを予防するためには、主に以下の4つを行いましょう。
- ●トイレの水漏れは日々の掃除で予防する
- ●薬剤などで配管のつまりを除く
- ●定期的にネジやナットなどを締めておく
- ●過度な節水に注意する
トイレの水漏れは日々の掃除で予防する
こまめに掃除を行うことで、部品交換のタイミングを早めに検討することができるようになります。
パッキンなどが劣化すると周囲に汚れが出る部品もあるため、汚れ具合を一つの目安にすることも可能です。
便器だけでなくタンクの中も掃除することで、溜めている水量や防露材の膨らみを確認して結露の具合などを確かめるのも良いでしょう。
薬剤などで配管のつまりを除く
上述の逆流を防ぐためにも排水管や排水桝などのつまりは、なるべく抑えるのが理想です。
定期的に塩素系薬剤などを使用し、排水管に汚れが着くのを防ぐようにしましょう。
排水桝などの一般家庭ではなかなか手を出しづらい場所は、業者に依頼して高圧洗浄などで掃除してもらうのがおすすめです。
定期的にネジやナットなどを締めておく
先述のように、小さな衝撃を与えられ続けることでネジやナットが緩んでしまうことがあります。
そのため、定期的に締め直すようにしましょう。
また地震などの災害があった場合は振動などにより一気に緩んでしまうこともあるため、注意が必要です。
過度な節水に注意する
節水のためにタンクにペットボトルを入れている方もいらっしゃいますが、タンク内の水は一定の水量が入るよう計算されて作られているため、逆に故障や水漏れを引き起こす原因になりかねません。
また適切な水量や水の勢いがなければ、トイレットペーパーや汚れが流されない場合もあり、排水管のつまりを引き起こしてしまう可能性もあります。
過度な節水はせず、適量の水を使用するようにしましょう。
大雨の時にだけトイレが水浸しになる場合の対処法

普段は何もないけれど、雨の時だけトイレが水浸しになるという場合は、逆流現象が起きている可能性があります。
それでは、逆流現象についての解説と対処法についてご紹介します。
下水が逆流している
ゲリラ豪雨などにより水量が短い期間で極端に増え、下水の処理能力がパンクしてしまうことで、各家庭の下水を遡って逆流してしまうことがあります。
各家庭の配管の配置として、トイレの排水管は下水に繋がる最終地点になっている場合が多く、逆流してきた際に最初に水が溢れ出やすくなっているのです。
地域や家の立地条件などにより逆流の起こりやすさは変わるため、家を建てる際は不動産の方とよく相談しておきましょう。
ゴポゴポと嫌な音がしたら逆流の前兆
トイレの水が逆流してくる際の前兆として、「ゴポゴポ」と嫌な音が聞こえてくる場合があります。
これは配管の中に残った空気が下水に押されて、便器内の水を揺らしていることが原因です。
このような音が聞こえる場合、下水の処理能力が追いつくまで水の使用はなるべく控えるようにしましょう。
逆流に気づいたら止水栓を閉める
逆流のみならず水漏れに気づいたら、まず止水栓を閉めて一時的にトイレの水の供給を停止させましょう。
新しい水を供給し続けていると、漏れる水の量も多くなり、被害が広がる恐れがあります。
水の供給を一時的に止める場合、止水栓を閉めることでトイレ周辺の水だけを止めることが可能です。
その際に、止水栓を何回転させて閉めたかを覚えておきましょう。
修理を終えて再度止水栓を開ける際に、間違って水量を出しすぎてしまうことがあります。
水の勢いなどを見ながら、ゆっくりと開けるようにしましょう。
水のうで逆流を抑える
災害時、「水のう」を便器の中に沈めておくことで逆流を抑えられます。
水のうを作る際は、45リットル程度のごみ袋をニ、三重に重ねて簡単に破けないように補強してください。
そして、ごみ袋の半分ほどの水を入れてから口を硬く締めます。
水はおよそ20リットルを目安に、ごみ袋いっぱいまで入れないように注意しましょう。
水のうを便器の中に入れておくと重いフタをしている状態であるため、下水からの水が溢れて水浸しになる被害を抑えることができます。
水をなるべく流さない
逆流の心配がある場合は、トイレの使用をなるべく控えて水を流さないようにしましょう。
下水が追いついていない状態でさらに水を流すと、水が溢れてきてしまう恐れがあります。
いざという時のために、あらかじめ避難場所や高台にある店舗などのトイレを確認しておきましょう。
また断水などに備えて、水を溜めておくというのもおすすめです。
まとめ
ここまでトイレが水浸しになる原因についてご紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。
トイレを水浸しにしないためには、普段から排水管などの掃除をこまめに行い、汚れなどが配管に張り付くのを防ぐことが必要です。
また排水管などの寿命を鑑みて、定期的に業者によるメンテナンスを受けましょう。
雨が降った時だけ水浸しになる場合は、なるべく逆流を防ぐように努めることが大事です。
逆流が起こってしまった際は、汚水に触れないようにし、いざという時のために避難場所も確認しておきましょう。
トイレが水浸しになってお困りの方は、ぜひ「しずおか水道職人」へご相談ください。
水道局が指定している業者のため、しっかりとした見積もりを出し、不当な高額請求などは一切行いません。
作業は必ず了承を得てから行うため、お気軽にご相談ください。
静岡のトイレのつまり・水漏れは、水道修理の専門店「しずおか水道職人(静岡水道職人)」
静岡市
浜松市
沼津市
熱海市
三島市
富士宮市
伊東市
島田市
富士市
磐田市
焼津市
掛川市
藤枝市
御殿場市
袋井市
下田市
裾野市
湖西市
伊豆市
御前崎市
菊川市
伊豆の国市
牧之原市
賀茂郡
田方郡函南町
駿東郡
榛原郡
周智郡森町
その他の地域の方もご相談ください!